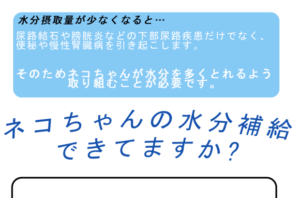東洋医療科担当の増田です。前回は、漢方とは何なのか?世間にたくさん存在する漢方について、中成薬と日本漢方、保険診療で使用される漢方と漢方薬局で使われる漢方のとの違いについてご紹介しました。今回は小動物の医療現場で漢方を使用した例などについてご紹介します。
動物の漢方はどのように使われているの?

皆さん(人間)が漢方を服用するのはどんな時でしょうか?病気やケガなどで医療機関にかかったときのほか、セルフケアとして使用されることも多いように思います。動物の場合でも使用目的は同じで、治療を目的としたものから日頃の健康維持まで幅広く応用されています。抗がん治療と併用されることもあり、副作用の軽減に漢が役立てられることもあります。
動物での漢方の使用が多いケースとして、消化器の症状(嘔吐、下痢、食欲不振、肝臓の不調)、皮膚(特に慢性のアレルギー疾患)、筋肉や骨格の痛みや不調、原因がよくわからない不調、老化に伴う衰えが挙げられます。割と幅広く応用が出来ます。
とはいっても漢方のみで改善が見込めないものもあります。例えば、骨折や外傷などは外科処置が必須ですし、腫瘍によっては外科手術で根治ができるものもありますので、オールマイティーではありません。そのため、西洋医療、東洋医療の良いところを適切なところで使用することが望ましいのではないかと考えています。
漢方に対するイメージ、これ本当?

一般に漢方は、「からだにやさしい」「副作用がないから安心」「ゆっくり作用する」「長期間飲まないと効果がない」「おいしくない」と思われていることが多いです。いろいろな人から漢方のイメージをお尋ねすると、このような答えがほとんどを占めます。
これらは正しい部分もあり、実はそうでもないといえるところがあります。漢方は生薬と呼ばれる薬理作用のある植物あるいは動物、鉱物を使用していますがその体に与える影響はわずかなものから非常に強力あるいは毒性の強いものまであります。それをなるべく悪い影響が出ないように長い月日をかけて確立されたものが漢方薬ですが、甘草という生薬を含む漢方薬は「偽アルドステロン症」という倦怠感や血圧上昇を招く場合があります。
そのため、体の状態をしっかりと評価したうえで漢方を選び使用することが重要となります。動物の場合自覚症状が判断しにくいことがありますので、専門知識を持った者からのアドバイスを受けるようにしましょう。
味に関して、甘いものから苦味の強いものまであります。漢方に限らず薬として世に出ているものは苦い成分が多いのですが、苦味の強いものを甘さでカバーするよりやや苦みのあるものをうまく活用する方が、味を感じにくくなることがあります。飲ませ方などもお気軽にご相談ください。
漢方治療により改善した例
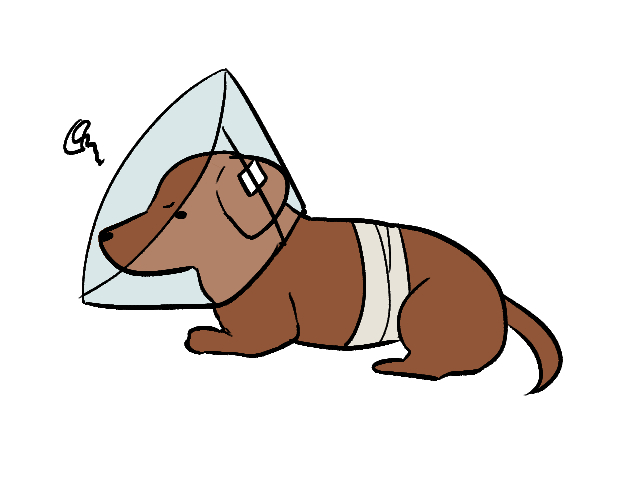
甲状腺ホルモン分泌機能が不安定なわんこで、全身の脱毛が生じ、かゆみ止めとしてステロイドによる治療歴のあるわんこです。かゆみは幾分薬の影響で改善するもののステロイドによる影響で皮膚が薄くなる影響が生じており、ご相談を受けました。
全身、特に四肢の冷えと皮膚の乾燥が強く、血色がやや白いことや脈の強さなどから「気血両虚」と呼ばれる状態と判断し、それに準じた漢方を使用しました。
2か月後、発毛がみられ地肌が見える状況になるまで改善しました。
鍼灸と漢方治療により改善した例
他院さまで胸椎の椎間板ヘルニアと診断されたわんこです。重症度はグレード3で鍼灸をご希望され鍼と漢方を使用して治療を行いました。歩行の改善がみられたほか、早期の機能回復と再発予防を目的として漢方を使用しています。後肢の麻痺は東洋医学では「痺」や「萎」と呼ばれます。不調となった経緯や、その時点での血流の具合などから漢方を選び処方します。椎間板ヘルニアの養生で漢方を処方することが多いのですが、同じ疾患であっても症状や年齢、既往歴や体質によって使用する漢方に違いが出ることがあります。
てんかんの漢方使用例

時折てんかんの発作を生じるチワワちゃん。抗てんかん薬との相性が芳しくないことがあり、漢方および鍼灸で治療を行っております。
完全に発作を抑えるところまでには至っていませんが、漢方の服用とりわけ季節の変わり目や著しい気候変化が生じうる時に鍼灸も併用して維持をしています。
漢方は病名だけではなくからだの状態に合わせて使用するのが特徴
漢方の治療を行うときに、処方している漢方の服用量がたびたび変わることがあるばかりか、漢方そのものの内容や組み合わせが変わることもあります。漢方の治療で特徴となるのは、治療を通じてからだに変化が現れたときは、そのときに状況に合わせた「証」による処方をするという所です。そのため、適切なタイミングで診察を行い、からだの状況を把握してさらに良いコンディションを作れるような取り組み方をしています。
ご不明点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。