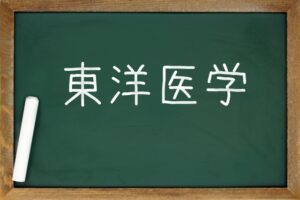9月は、暦の上では秋に入る時期といわれますが、日本ではまだ暑さが厳しい状態ですね。とはいえ、ゆっくりと秋の気配も感じられるようになりました。日中と朝晩の気温差が大きくなる時期です。東洋医学では「長夏(ちょうか)」から「秋」へ移り変わる季節とされ、この時期は体調を崩しやすい特徴があります。特に犬猫にとっても、消化器系や呼吸器系の不調が出やすいため、日頃からの養生が大切です。
9月に多い不調と東洋医学的な解説
東洋医学では季節ごとに体に影響を与える「五行」があります。9月は「脾(消化器系)」と「肺(呼吸器系・皮膚)」が影響を受けやすい時期です。
消化器系の不調
夏の暑さ対策でエアコンを使います。からだが冷えすぎると「脾胃(ひい)」が弱り、食欲不振や軟便が見られることがあります。犬猫も同様で、フードの食べ残しや下痢・嘔吐といった症状が出やすくなります。
呼吸器系・皮膚の不調
秋は「燥(乾燥)」の季節であり、肺に影響します。乾燥は咳や鼻の不快感だけでなく、皮膚や被毛のパサつき、かゆみを引き起こす原因になります。特にアレルギー体質の子やシニア犬猫では注意が必要です。
気温差による体調変化
朝晩と日中の気温差で「陽気(体を温める力)」が消耗しやすく、免疫力が下がりやすい時期です。夏の疲れが出て体がだるそうに見えることもあります。
ご家庭でできる9月の養生ポイント
食事
消化に優しいフードを心がけ、冷たい食べ物やおやつを避けましょう。秋の旬食材の中で犬猫に適したもの(さつまいも、かぼちゃなど)は「脾」を助ける働きがあり、おやつやトッピングに少量取り入れるのがおすすめです。療法食をご利用の際は、獣医師にご確認ください。
環境
日中はまだ暑くても、夜は冷え込むことがあります。体温調整がしやすいよう、寝床にはタオルや毛布を用意し、冷えすぎないようにしてあげましょう。
プラスアルファのケア
ブラッシングで皮膚の血流を良くし、乾燥対策を意識します。感想が気になる場合は加湿器を使用して適度な湿度を保つことも、秋の「燥」を和らげます。
飼い主さんでもできる!おすすめツボ3選
ここでは、犬猫に応用しやすいツボを3つご紹介します。軽く指で押す・マッサージするように刺激してみてください。1日1〜2回、優しく行うのがポイントです。
足三里(あしさんり)
前足の肘を曲げた時にできるしわから、やや下外側にあるツボ。胃腸の働きを整え、元気を補う代表的なツボです。夏バテや食欲不振が気になる時におすすめです。

【足三里:膝の関節より少し前下方にあります】
合谷(ごうこく)
前足の甲側、第1指と第2指の間にあるツボ。体全体のバランスを整え、免疫力を高める働きがあります。季節の変わり目に体調を崩しやすい子に役立ちます。

【合谷:親指の付け根の部分を軽くマッサージします】
肺兪(はいゆ)
背中の肩甲骨のやや下、背骨の両脇にあるツボ。呼吸器や皮膚の不調に関係するツボで、乾燥による咳や皮膚トラブルがある時に有効です。ブラッシングの時に軽く撫でるように刺激すると良いでしょう。

【肺兪:呼吸器だけでなくからだの免疫力強化にも役立ちます】
まとめ
9月は季節の変わり目で、犬猫の体にも負担がかかりやすい時期です。東洋医学の視点からは、「脾」と「肺」を養うことがポイントになります。食事や生活環境を少し整えるだけで、体調不良の予防につながります。ツボ押しやマッサージも取り入れ、愛犬・愛猫が健やかに秋を迎えられるよう、ぜひご家庭で実践してみてください。