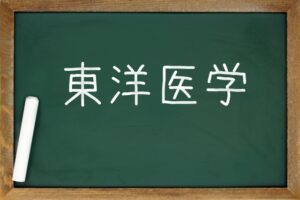10月は秋も深まり、朝晩の冷え込みが一段と強まる時期です。夏から秋への変化で体調を崩した犬猫に加え、乾燥や寒暖差の影響が出やすい季節でもあります。東洋医学ではこの時期を「燥邪(乾燥)」と「寒邪(寒さ)」が入り込みやすい季節ととらえ、体を潤し、ほどよく温めることが大切とされています。
10月に多い不調と中医学的な解説
秋の主な臓腑は「肺」。肺は呼吸器だけでなく、皮膚や被毛、からだを守る防衛機能、つまり免疫にも関わる重要なところとされています。乾燥は肺を弱らせ、「皮膚のかゆみ」「被毛のパサつき」「咳」「鼻水」「涙やけ」などの症状が出やすくなります。特にアレルギー体質や高齢の犬猫では、皮膚バリアが弱まりやすく、湿疹やかゆみが悪化することがあります。
一方で、朝晩の冷え込みが増すことで「冷えによる血の巡りの悪さ」も目立ってきます。冷えは気や血の流れを滞らせ、関節のこわばりや腰痛、シニア期に多い関節炎の悪化を招くこともあります。中医学ではこれを「寒湿」の影響ととらえ、体を温めて流れを良くすることが重要です。
また、10月は「気温の下降」に体が追いつかず、免疫力が低下する時期でもあります。犬猫がなんとなく元気がない、食欲が落ちる、寝てばかりいる…といった変化も、季節の影響による「気や血の乱れ」が原因かもしれません。
ご家庭でできる10月の養生ポイント
・体を冷やさない工夫を
朝晩は気温が下がるため、寝床にふわっとした毛布やクッションを追加しましょう。床からの冷えは関節トラブルの原因になるため、ベッドを少し高くしたり、マットを敷くのもおすすめです。
・潤いを意識した食事を
乾燥対策には、「肺」を潤す食材を取り入れるとよいでしょう。犬猫用としては、白ごま、さつまいも、れんこんなどを少量トッピングするのがおすすめです。これらは体をやさしく潤し、咳や皮膚の乾燥を防ぐ働きがあります。
・無理のない運動を続ける
涼しくなって過ごしやすくなる10月は、運動不足解消にも良い時期です。ただし、冷えた朝夕の散歩は筋肉が硬くなりやすいので、準備運動として少し体を温めてから外に出ましょう。
ご家庭でできる!おすすめツボ3選
風門(ふうもん)
肩甲骨の内側、背骨の両脇あたりに位置するツボ。風邪(外からの風邪邪気)を防ぎ、免疫を高める働きがあります。ブラッシングの際に背中を撫でるように刺激すると、体表の気の巡りが整いやすくなります。

【風門:咳を鎮めるほか、頸部や肩の痛みの軽減にも役立ちます】
腎兪(じんゆ)
腰のやや上、背骨の両脇にあるツボ。冷えからくる腰や後肢のだるさ、関節痛に効果的です。特にシニア犬や寒がりな猫ちゃんにおすすめで、手のひらで温めるように軽くマッサージあるいは温灸やホットパックなどが活用できます。

【腎兪:アンチエイジングや腰痛など幅広く活用できるツボのひとつです】
太谿(たいけい)
後足の内側、アキレス腱と骨の間にあるツボ。腎の働きを補い、冷えや老化の予防に役立ちます。冷えが強い子には、湯たんぽやホットタオルで温めながら優しく触れると効果的です。

【太谿:内側のくるぶしの上方にあるくぼみです。反対側のツボの崑崙と合わせて挟んでマッサージすると便利です】
まとめ
10月は、乾燥と冷えが同時に進む季節。東洋医学では「潤いを守り、冷えを防ぐ」ことが養生の鍵とされています。食事や住環境を少し工夫し、ツボマッサージを取り入れることで、犬猫の体調を整えやすくなります。
秋の深まりとともに、体も心も落ち着く時期。季節の変化を上手にサポートし、愛犬・愛猫が健やかに秋を過ごせるよう心がけてあげましょう。